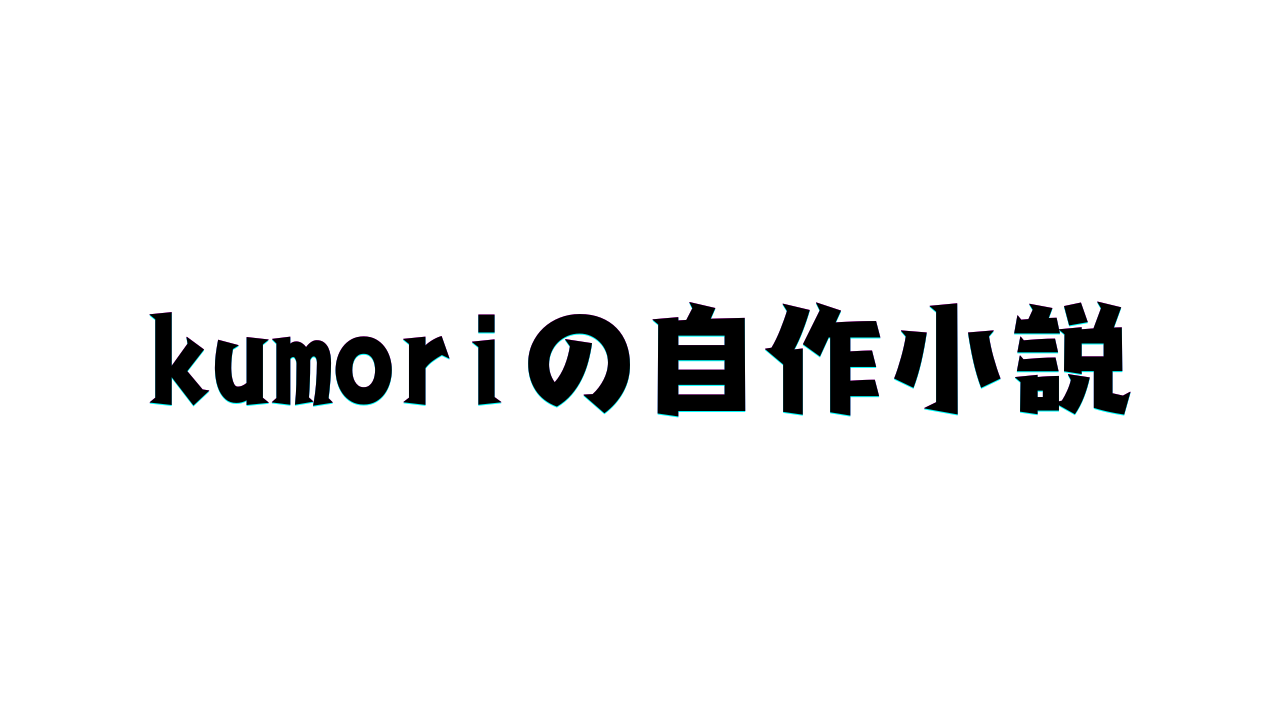START

「3回戦・適性診断」が終わり、観覧車のゴンドラがゆっくりと地上へと降りた。
扉が開き、終打は降りようとすると・・・
老人
「失礼。」
白髪の老人が、終打のゴンドラに乗り込んできた。
老人は静かに腰を下ろし、終打の向かいの席に座ると、やわらかな声で語り始めた。

老人
「斉堂終打くん。君に会うのを、ずっと待っていた。」
終打の眉がわずかに動く。
終打
「…あなたは?」
老人は微笑んだ。
老人
「私は”TypeFes”の主催者であり、昔、君の父”斉堂透夜”と共にAIの研究に携わっていた者だ。」
「色々と聞きたいこともあるだろうが、まずは私の話を聞いて欲しい。」
「今の社会は、ほぼすべての業務がAIによって処理されている。ニュースの作成、建設計画、
医療診断、裁判の判例整理。もはや人間は、AIに何を”させるか”を指示するだけになった。」
「だが、その”指示”をどう伝えるか。そこに、大きな分かれ道がある。」
終打
「伝え方はタイピングだけではないのですか?」
老人
「それが違うんだ。最近、新しい方式が”とある集団”によって開発された。」
「終打くん、”VOICELINK”という名前を聞いたことはあるかい?」
終打
「聞いたことないです。」
老人
「”AI研究のプロフェッショナル”を集めて作られた、精鋭の頭脳集団の名前なんだ。
彼らはAIを、声ひとつで思い通りに操る技術を持っている。
普通の人間にはできないことを、簡単にやってのける。」
「つまり、新しい方式とは、”音声認識”なんだ」
「だが、彼らはその力を”正しいこと”には使わず、世界の重要情報を抜き取ることに使っている。
今、世界中の企業や街が、声だけで操れるAIの暴走に怯えているんだ。」

「ほとんどの人間は、タイピングの速さより、声の方が速く指示を出せる。」
「つまり、タイピングが音声認識に勝つためには、
“声を凌駕するタイピングスピード”を持つ必要があった。」
「そして、私は”TypeFes”を開催し、VOICELINKに一矢報いることが出来る人間を探した。」
「その結果、本選出場者100名の中から、君が選ばれた。」
終打
「純粋なタイピングスピードだけなら、今回の100名全員、声より速いのでは?」
老人
「そうだね。だけど、音声認識に打ち勝つためには、他の要因も必要だった。」
「タイピングスピードを見るだけなら、予選の内容だけで十分だ」
「これまでの試験内容全ての趣旨を説明しよう。」
後半はこちら↓